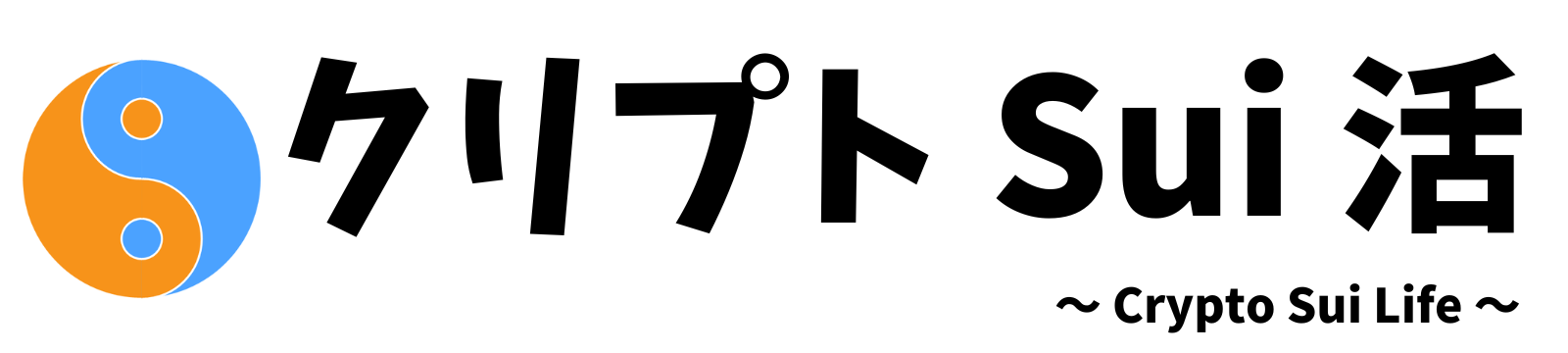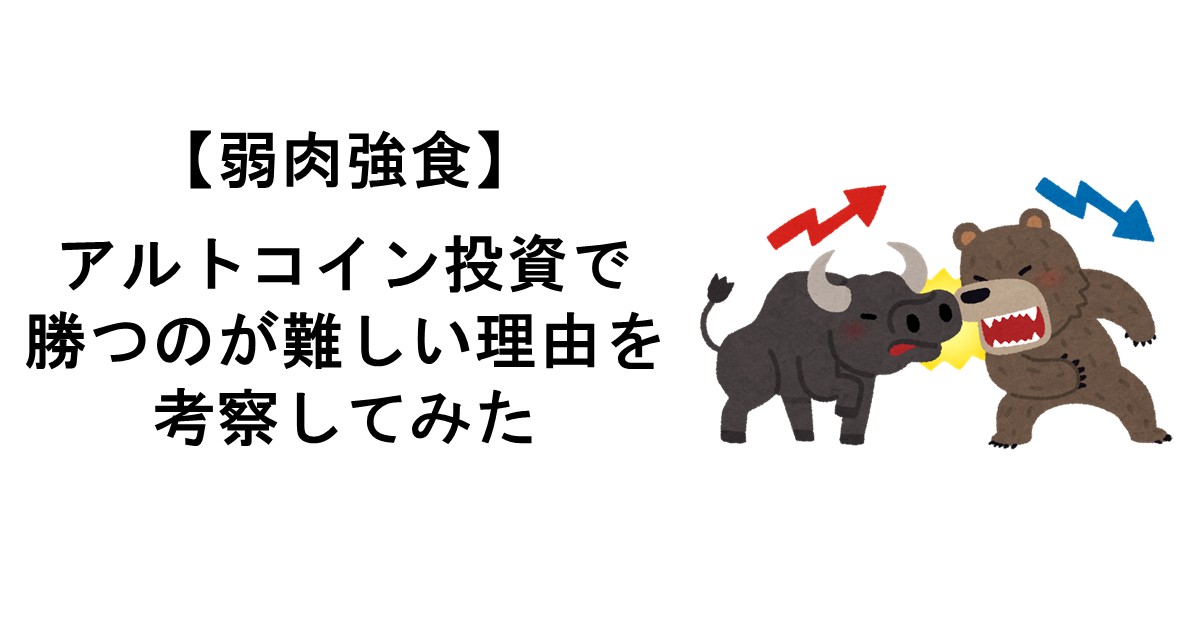こんにちは、Yohです。
暗号資産(仮想通貨)は一般に、ビットコインとそれ以外のアルトコインに大別されます。
特にアルトコインは、株やビットコインに比べて価格上昇時の倍率が高いため、夢とロマンを求めて多くの人が投資しているアセットです。
一方、アルトコインに投資してしまったせいで、資金を失い、市場からの退場を余儀なくされる人も後を絶ちません。
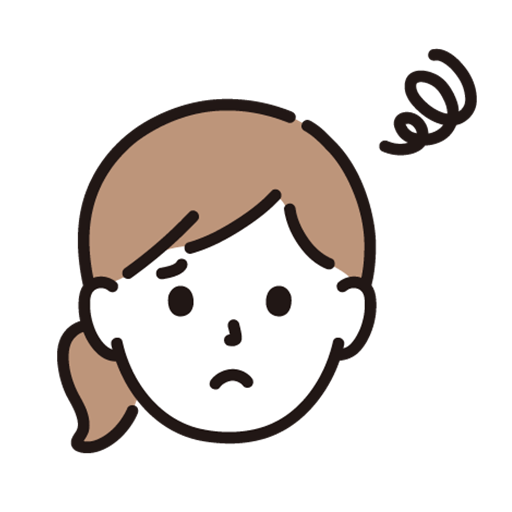 クリプト初心者
クリプト初心者誰でも当事者になりえるわけで、ある意味恐ろしい世界…
現物投資の対象としては、間違いなくトップレベルのハイリスク・ハイリターン商品と言えるでしょう。
では、そもそもなぜアルトコイン投資はこんなに難しいのでしょうか?
今回は「ハイリスク・ハイリターンだから」だけで片付けずに、僕の実体験も踏まえつつ、その要因を考察してみようと思います(自戒もこめて)。
要因を2つに大別する
アルトコイン投資の難しさを考えるために、今回は5W1Hをベースに次のような切り口を用意することにします。
- 「どの銘柄」に投資するか?(What)
- 「いつ」投資するか?(When)



「なぜ?」(Why)は両者を考える中で必然的に出てくる話なので、ここには明記していません。
「どこで」(Where)や「どうやって(How)」については、例えば「どの取引所を使うか」という話であり、ビットコイン・アルトコイン共通の議題なので、今回は省略します。
切り口1:「どの銘柄」に投資するか?(What)
理由1:銘柄選びが難しい
アルトコイン投資が難しい理由の1つ目として、そもそも「銘柄選びが難しい」ことが挙げられます。
アルトコインの種類はいくつも存在し、毎日のように新しいコインが生まれています。
例えば、国内大手取引所であるbitbankだけに絞っても、銘柄数は42(2025年5月時点)。
大きく上昇できる銘柄をピンポイントで選んでくることは、決して簡単ではありません。
ちなみに銘柄選定のミスは、その後の市場生存率に致命的な影響を及ぼします。
例えば、国内取引所で扱っている銘柄で有名なものにXYM(シンボル)があります。
当時すでに有名だったNEM(ネム)の関連銘柄として2021年3月にローンチされましたが、チャートは見事に右肩下がり。


引用:TradingView
もし次回のバブル狙いで大金を投じていた場合、ほぼ全員が市場から退場することになるでしょう。
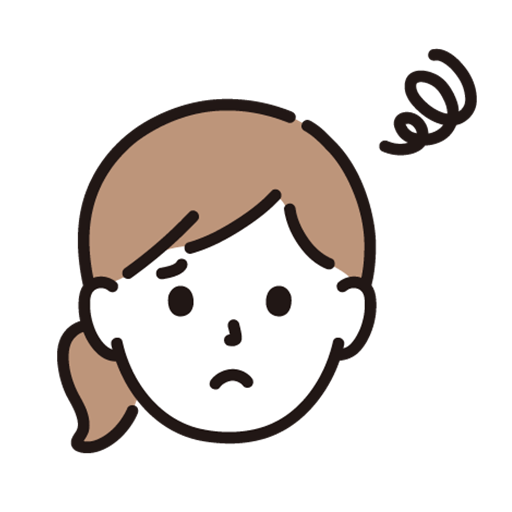
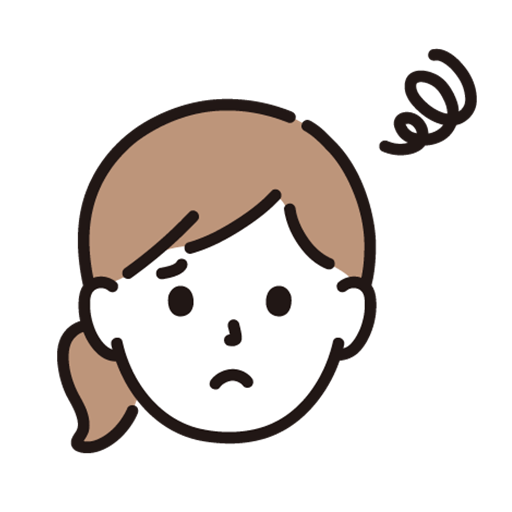
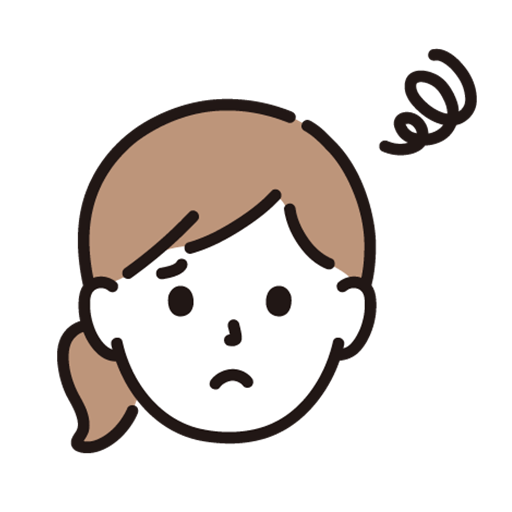
XYMはなぜこんなに下がってしまったんだろう?



公式サイトを覗いてみましたが、最終更新日は2021年11月30日。
おそらく開発やマーケティングがうまく進んでいないのだと考えられます。
理由2:ミームコインの存在
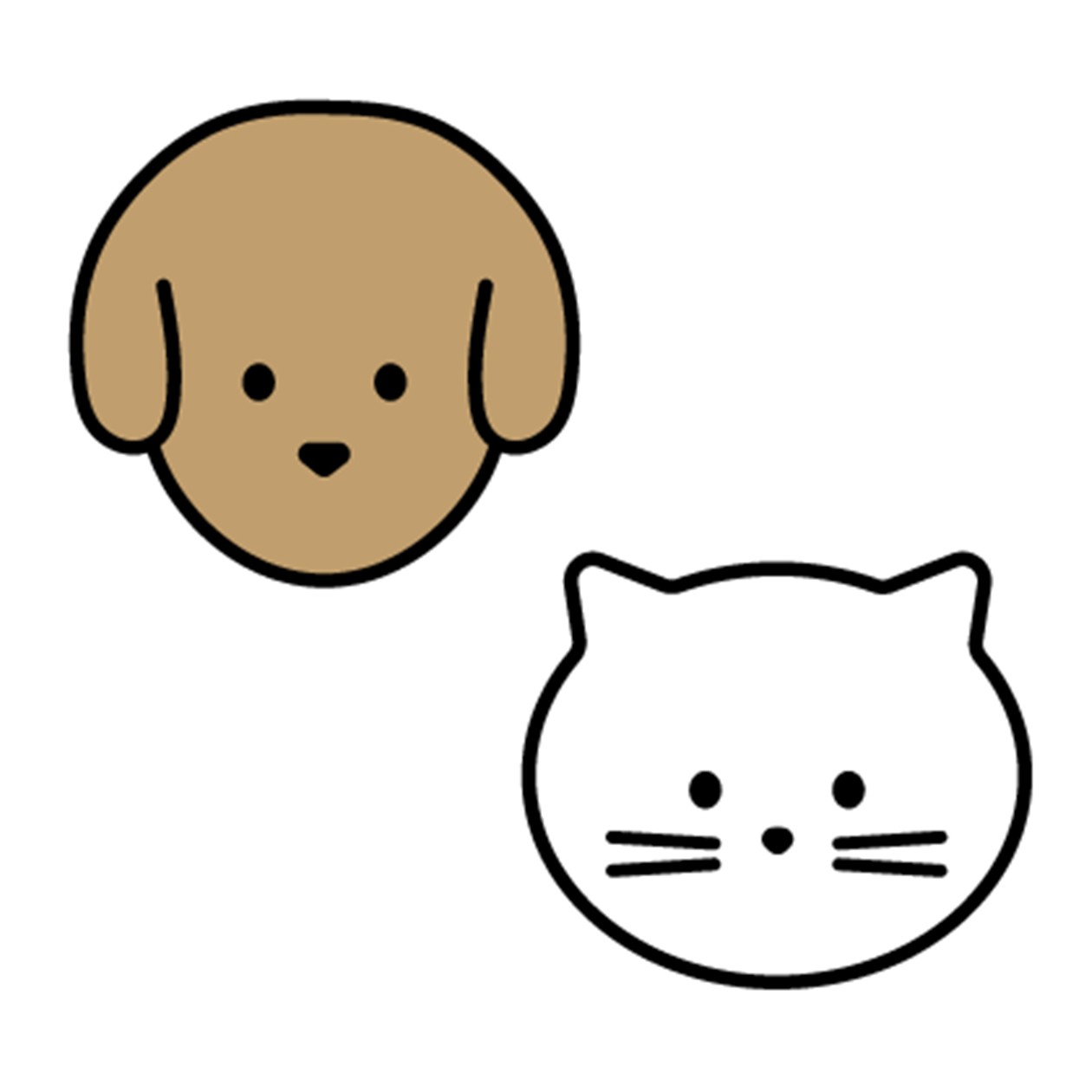
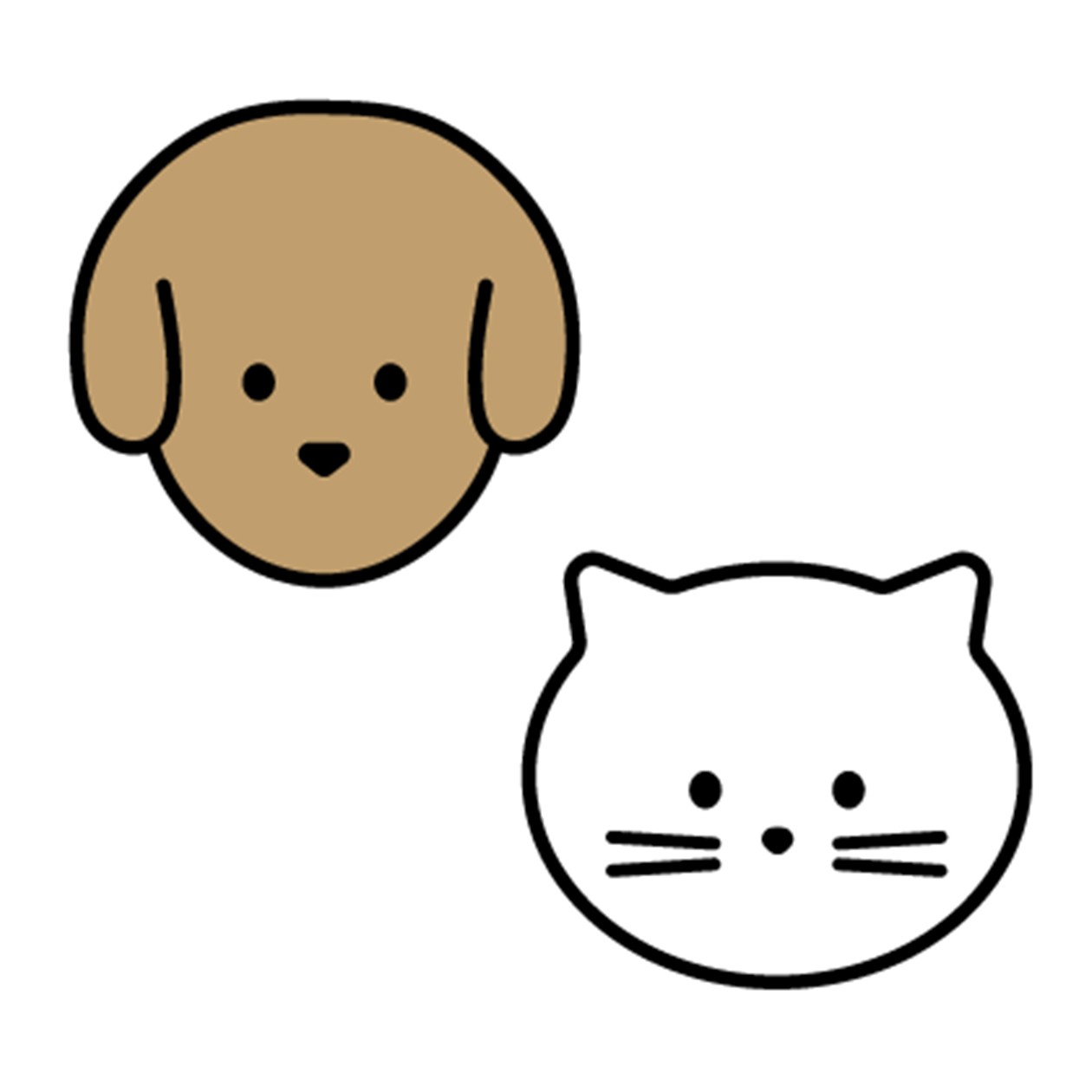
アルトコイン投資が難しい理由2つ目が、「ミームコインの存在」です。
ミームコイン(memecoin)とは、簡単に言うと、特定の目的やプロジェクトを持たない暗号資産(仮想通貨)のこと。
モノによっては、コミュニティの熱狂がSNS経由で伝播して、通常のアルトコインとは比較にならないほど大きな上昇を見せることがあり、一攫千金もありえるコインです。
そのため、ミームコインに手を出す人は後を絶ちません。
しかしながら、こうしたコインは時価総額が低く、下落時の下がり方も異常。
ホルダーのほとんどがコイン自体に価値がないことは理解しており、基本的に値上がり益のことしか考えていないので、悲観ムードが漂えばどんどん売却されてしまいます。
加えて、ミームコインには悪質なものも多く、発行者(運営)があらかじめ大量のトークンを保有しておき、価格を上がったところで全て売却して撤収してしまう、いわゆる「ラグプル」という手口が使われることがあります。
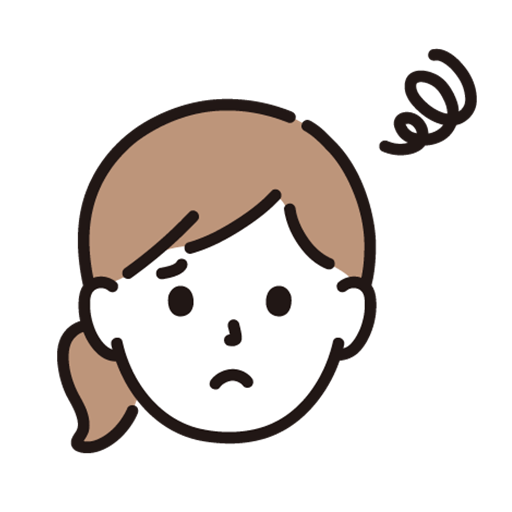
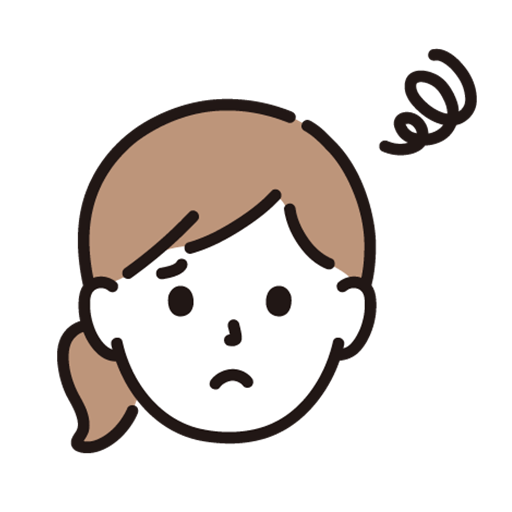
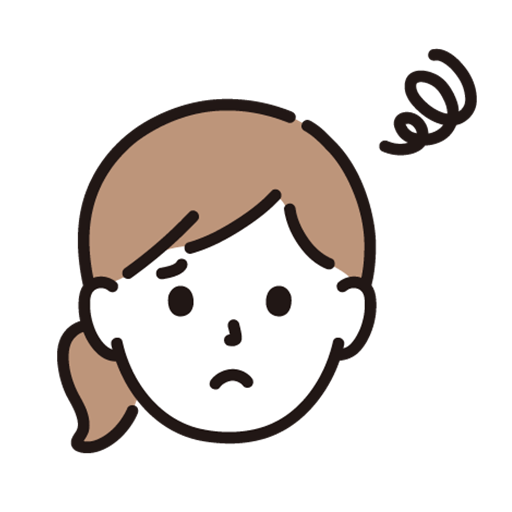
最近日本の証券会社で起きた不正アクセス事件の手口と似てるね。



事前にまともな運営・コミュニティなのかを見極める必要があります。
でもこれがまた難しい…
まとめると、ミームコインは大きな値上がり益を得られる可能性を秘めてはいますが、
- それ自体に価値がない
- 価格の上下(ボラティリティ)が異常
- 発行者(運営)がラグプルする場合がある
といったリスクを抱えているわけです。
リスクとリターンがつり合っていないので、このようなコインに大金を投じてしまうと、先に「握力が持たなくなる」か「塩漬けになる」のがたいていのケースとなります。



あくまで「宝くじ枠」と割り切り、少額で遊ぶ程度にとどめるのが無難かと思います。
(でもそのお金、他にもっと良い使い道があるのでは?)
理由3:インフルエンサーの発信内容で投資判断をしてしまう
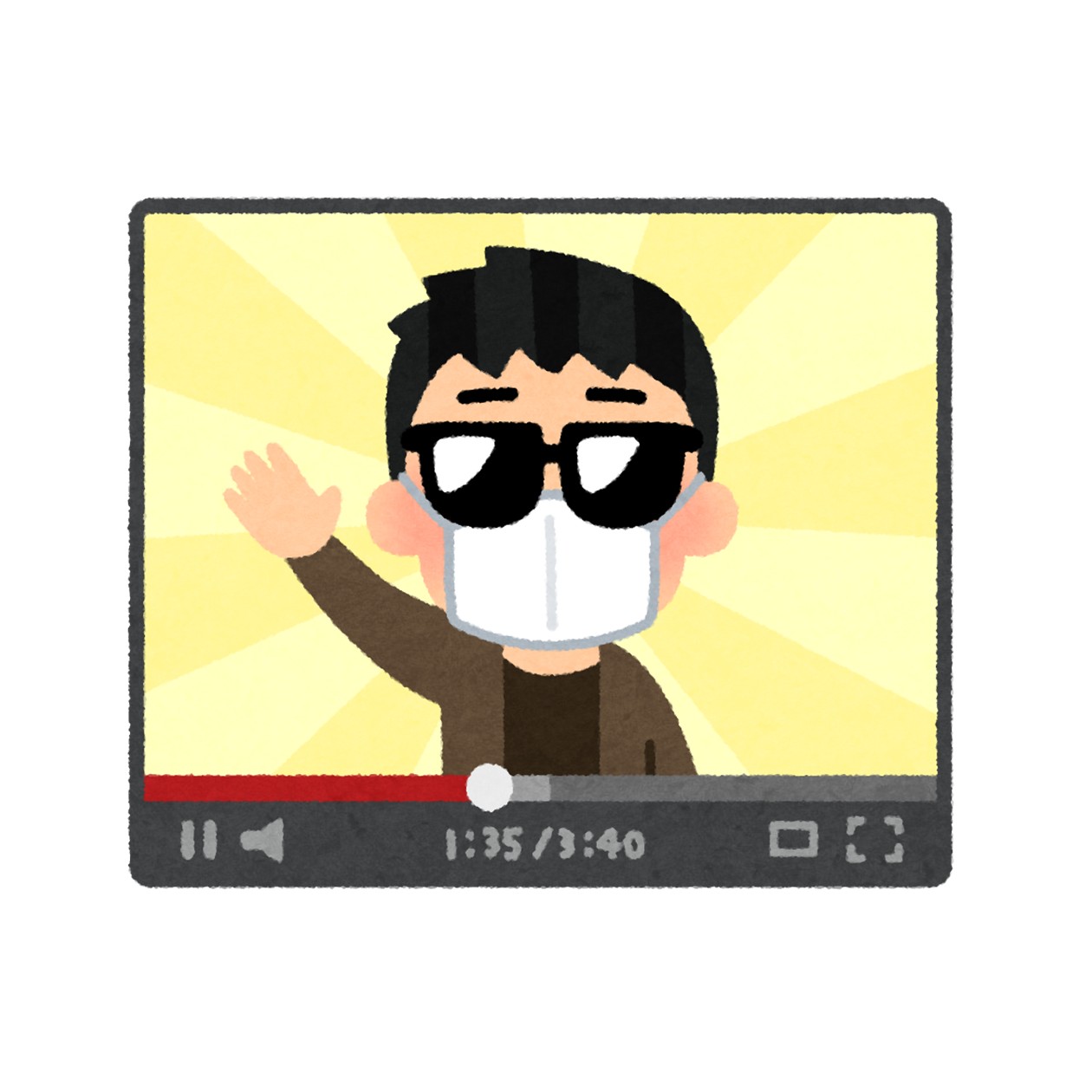
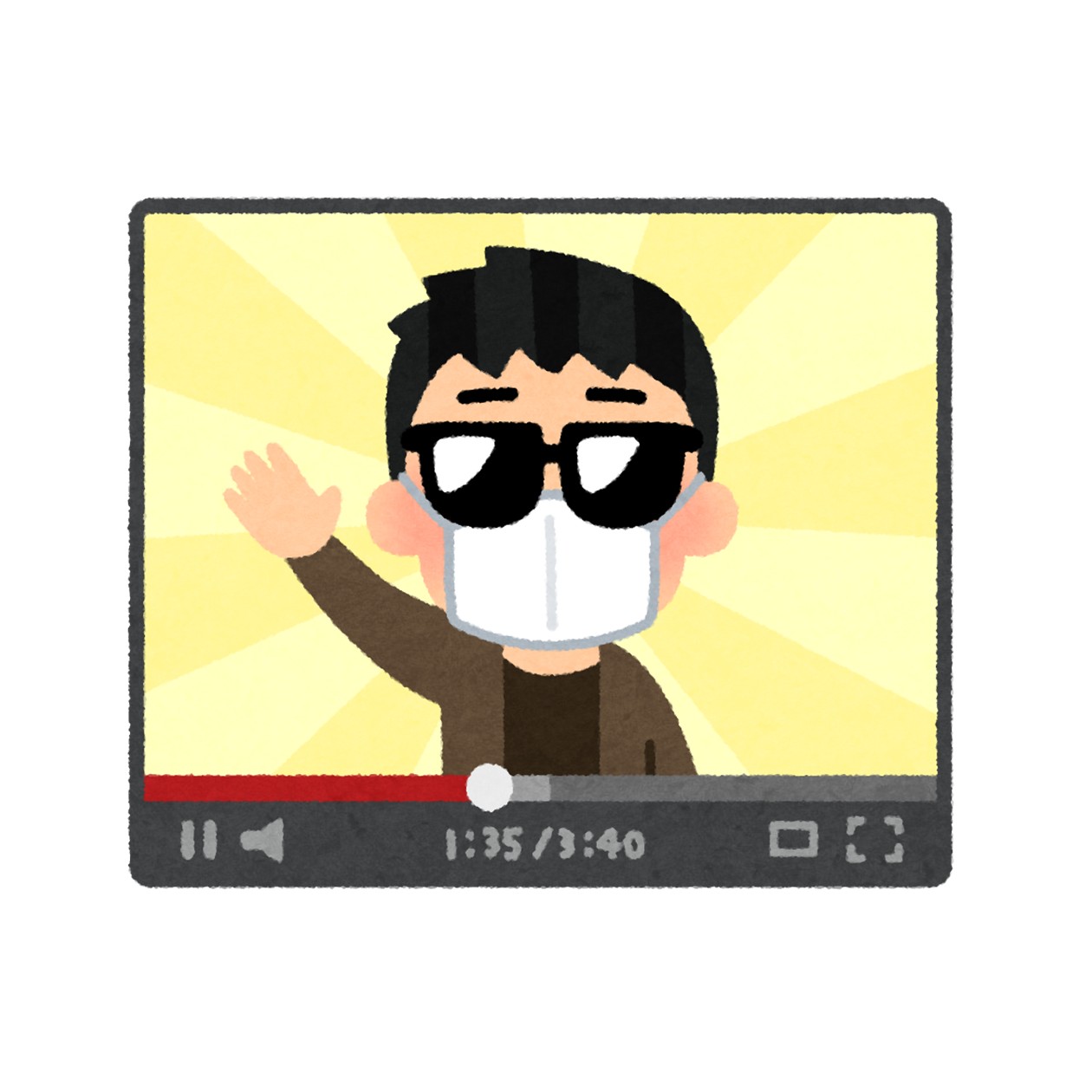
アルトコイン投資が難しい理由3つ目が、「インフルエンサーの発信内容で投資判断をしてしまう」です。
XやYouTubeでは、いわゆる仮想通貨インフルエンサーと呼ばれる人達がいます。
積極的に発信を行っているためフォロワー数が多く、情報収集のためにSNSを開けば、意図していなくても彼らの発信を目にする機会があるはずです。
仮想通貨インフルエンサー達は情報の察知だけはとにかく早いので、発信内容が有益である場合ももちろんあります。
しかし、インフルエンサーの言葉を鵜呑みにしてしまうと、投資判断を誤る可能性が高いです。
というのも、彼らの発信はまさしく玉石混交だから。
まず、内容や解釈に間違いが含まれることが非常に多いです。
主な理由として、彼ら自身も大元のソース(一次情報)を参照していなかったり、生存者バイアスがかかっていることが挙げられます。
また、中には「コミュニティやアフィリエイトへの誘導」といった、純粋な善意や期待感からではなく、自分の利益のみを目的にした発信もよくあります。
なので、「これから〇〇という銘柄が上がる or 下がる」とか「□□というコインを買えば億り人確定」みたいな発信を見た時、「有名なインフルエンサーが発信してる内容だし、信じても大丈夫だろう」と他責思考で判断すると、あとで痛い目を見ます。
「相場は誰にも予測できない」、「人によってリスク許容度や投資状況は異なる」という前提条件をしっかり覚えておく必要があります。



自責思考を忘れないようにしたいですね。
切り口2:「いつ」投資するか?(When)
理由4:流行のサイクルが早い


アルトコイン投資が難しい理由4つ目が、「流行のサイクルが早い」こと。
アルトコイン市場はその年によって注目されるジャンルや銘柄が異なるため、流行り廃りが激しい傾向があります。
実際に過去のデータを見ても、時価総額ランキング上位の顔ぶれは毎年結構変わっていることがわかります。
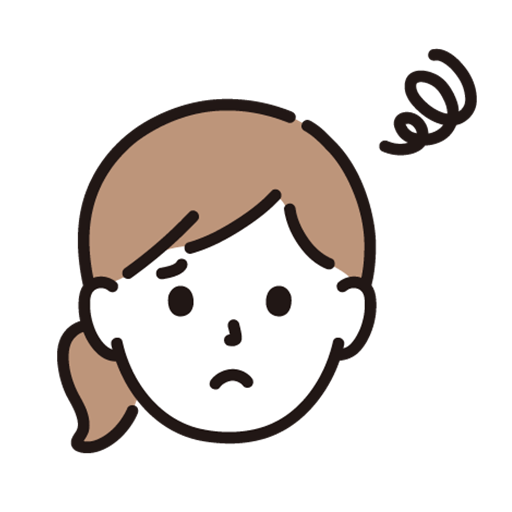
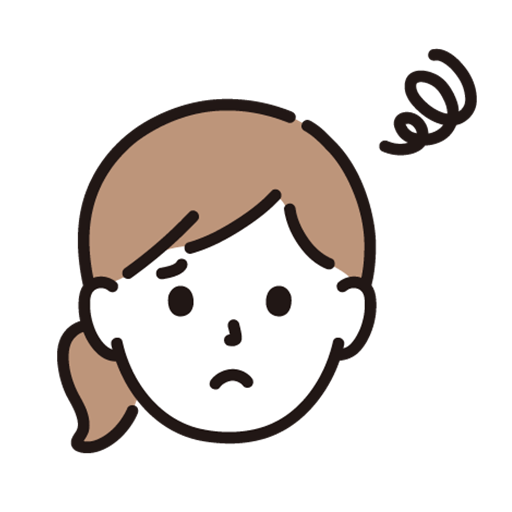
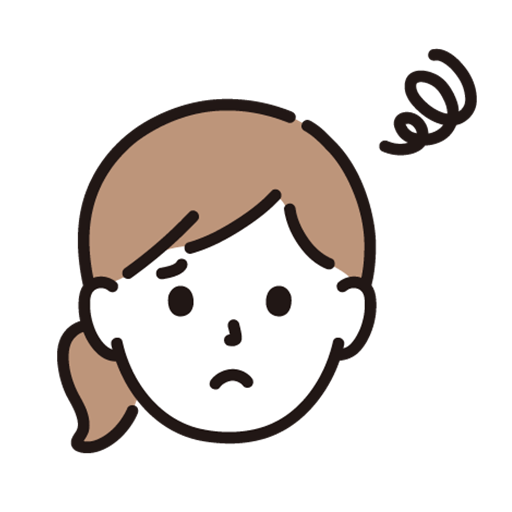
なんでこんなに順位が入れ替わるんだろう?



毎年高性能なブロックチェーンが登場しているのもありますが、やはり市場自体が新しい銘柄やジャンルを好むという点が大きいと思います。
こうした背景から、アルトコインに投資する際には、銘柄の期待値を分析するだけでなく、市場トレンドを踏まえて立ち回る必要も出てくるため、難易度が高くなってしまうわけです。
理由5:入口と出口のタイミングが難しい
アルトコイン投資が難しい理由5つ目に、「入口と出口のタイミングが難しい」ことが挙げられます。
期待できると確信した銘柄を見つけることができても、投資が上手くいくとは限りません。
結局、その銘柄を「どのタイミングで買って、どのタイミングで売るか」で最終的な勝敗が決まるからです。
当たり前ですが、価格が上昇している時に買ってしまうと、それは高値づかみとなり、利幅がとれません。
その上、下落時の安全マージンが少なくなるので、握力の低下を招き、結果として自ら損切りすることになります。



相場は誰にも読めないからこそ、タイミングの見極めが本当に難しい…
僕自身、ここで何度か失敗しているので、今回はそれらを紹介します。
【事例1:ARB(アービトラム)】


引用:TradingView
ARBはイーサリアムのL2銘柄として2023年頃から期待されていた銘柄で、bitbankに上場したタイミング(2024年12月)で初めて購入しました。
当初は順調に価格が上昇していきましたが、「2ドルは余裕で超えるでしょ!」という謎の判断で欲張り、2024年3月に追加投資。
結果はチャートを見ての通り、市場の地合いにつられて4月以降価格はどんどん下落していきました。
ARBについて調べ直した結果、自分の中での期待値が下がってしまったこともあり、結局2024年11月には損切りする羽目に。



お手本のような高値づかみをしてしまった銘柄です。
市場が勢いづいていた3月にこそ売却すべきでした。
【事例2:APT(アプトス)】


引用:TradingView
APTはSUIと同じMove言語を用いているブロックチェーン銘柄。
2024年11月にポジションを整理していた際、SUIに対する分散投資のつもりで購入しました。
当時はトランプ氏の大統領選が確定したタイミングで、チャートもダブルボトムを形成し始めていたことから、ある程度は利益が出せるだろうと考えていました。
こちらも最初は良かったのですが、12月20日のCEO退任発表を境に、チャートはどんどん悪化。
2025年に入っても価格が回復することはなく、結局2月には全売却して損切りを確定させました。



CEO退任は予測できないので仕方ないですが、1年で最も市場の調子が良いとされる11月に買ったことで、余計にリスクを高めてしまったのが反省点です。
どうすれば勝率を上げられるのか?
以上を踏まえた上で、アルトコイン投資で勝率を上げるためにできることを考えてみます。
余剰資金で投資する
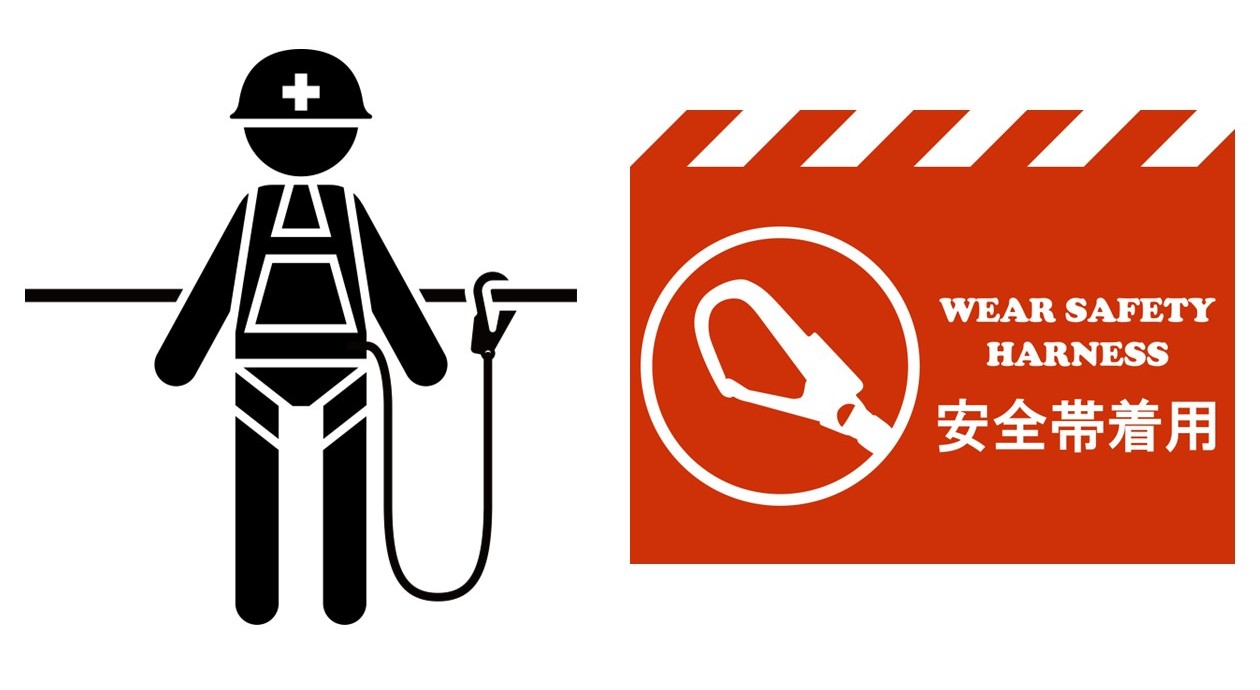
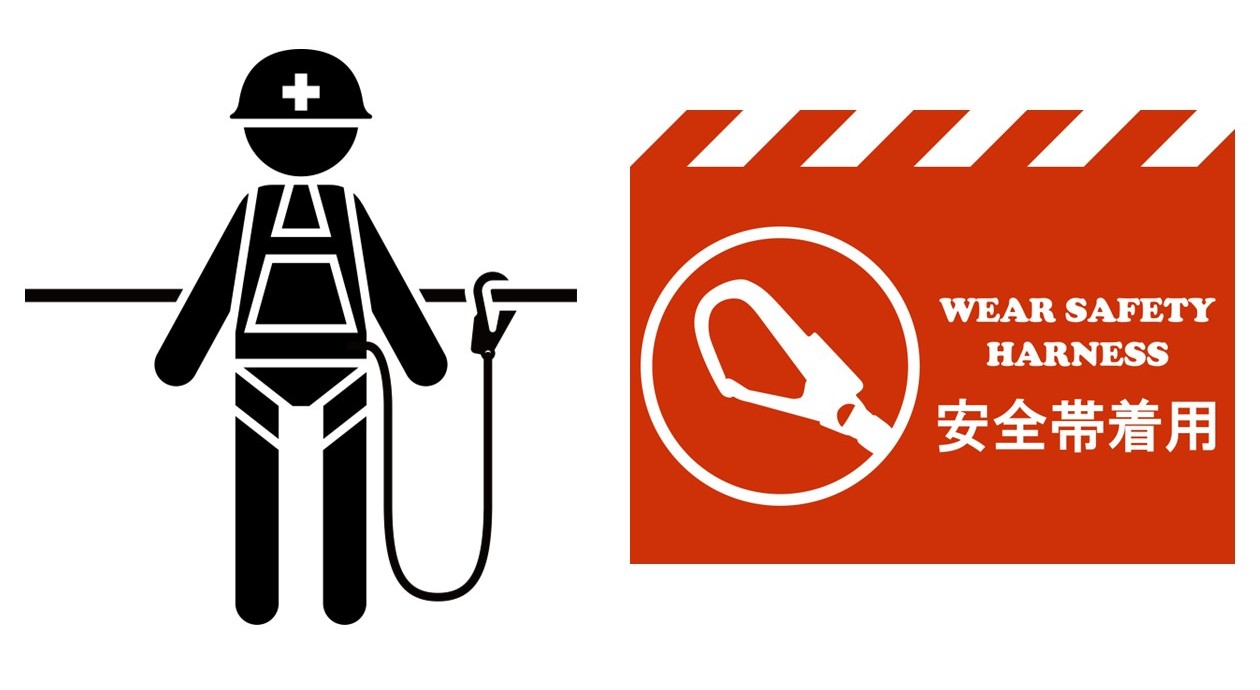
当たり前のことではありますが、他の投資同様、アルトコインへの投資は余剰資金で行うべきです。
リターンを追い求めるあまり、自分の許容範囲を超えて投資してしまうと、下落時のメンタルダメージが大きく、握力が持たずに損切りする羽目になります。
投資を始める前に、自分の資産状況・リスク許容度を十分に把握しておくことをオススメします。



自分が安心できるアセットアロケーション(資産別の配分比率)を見つけるといいですね。
銘柄を選ぶ時は自分でよく調べる


どのアルトコインが期待できるのかは自分でよく調べた上で判断することをオススメします。
時には他人の情報や意見を参考にするのも良いですが、やはり自分自身で一次情報にあたり、納得感を持って銘柄選定すると、短期的な値動きに一喜一憂せずに握力をキープできます。
そして何より、どんな結果になっても後悔が生まれにくいです。
市場に長く居続けるためのスキルとして身につけるべきでしょう。



個人的には、最悪長期保有することになっても構わないと思えた銘柄だけに投資するのがオススメです。
自分に合ったチャート分析法を身につける


投資で利益を出すには、安い時に買って高い時に売る必要があります。
ですが、市場の値動きを正確に予測することは誰にもできません。
まして底値で買って天井で売るなんてことは、まず不可能であると理解すべきでしょう。
それでも、チャートの分析手法を知っていれば、大きな過ちを犯す確率は減らせます。
分析法は無数にあるので、すべて習得しようとするとキリがないですが、自分が使いやすいと思えるものだけでよいので勉強しておくことをオススメします。



僕の場合はRSI(相対力指数)をよく使っています。
ポートフォリオにビットコインを組み込む
繰り返しになりますが、アルトコインの多くは時価総額が低いため、現物投資なのにまるでレバレッジ投資をしているようなレベルで値動きが激しいです。
SNSを見ている限り、歴の長いトレーダーの方ですら、価格によるメンタルの浮き沈みは大きいようです。
このことから、初心者がアルトコインだけに投資した場合、感情や資金をうまく管理できず、市場の養分にされる可能性も高いと考えられます。
そこでよく提案される対策として、「ポートフォリオ(投資配分)にビットコインを加える」というのがあります。
実際、暗号資産(仮想通貨)が生まれて以来、継続的に価格を上げ続けてこられた実績があるのはビットコインだけ。


引用:TradingView
ビットコインを持っておくことで、仮に保有しているアルトコインの調子が悪い時でも、それをカバーしてくれる可能性が生まれるわけです。



ビットコインは上がってるのにアルトコインは上がらないという場面がよくありますが、こういう時にビットコインを多少持っているとメンタルが楽になります。
Top Assets by Market Capによると、2025年5月時点でビットコインは時価総額ランキングで世界5位。
アルトコインに比べてずっと大きい時価総額を持つ(イーサリアムの約7倍)ため、価格変動率もメンタル負荷も相対的には小さいです。
アルトコイン投資で勝つための戦略として、ビットコインを活用するのも有効な手段だと言えます。
売買ルールを事前に決めておく
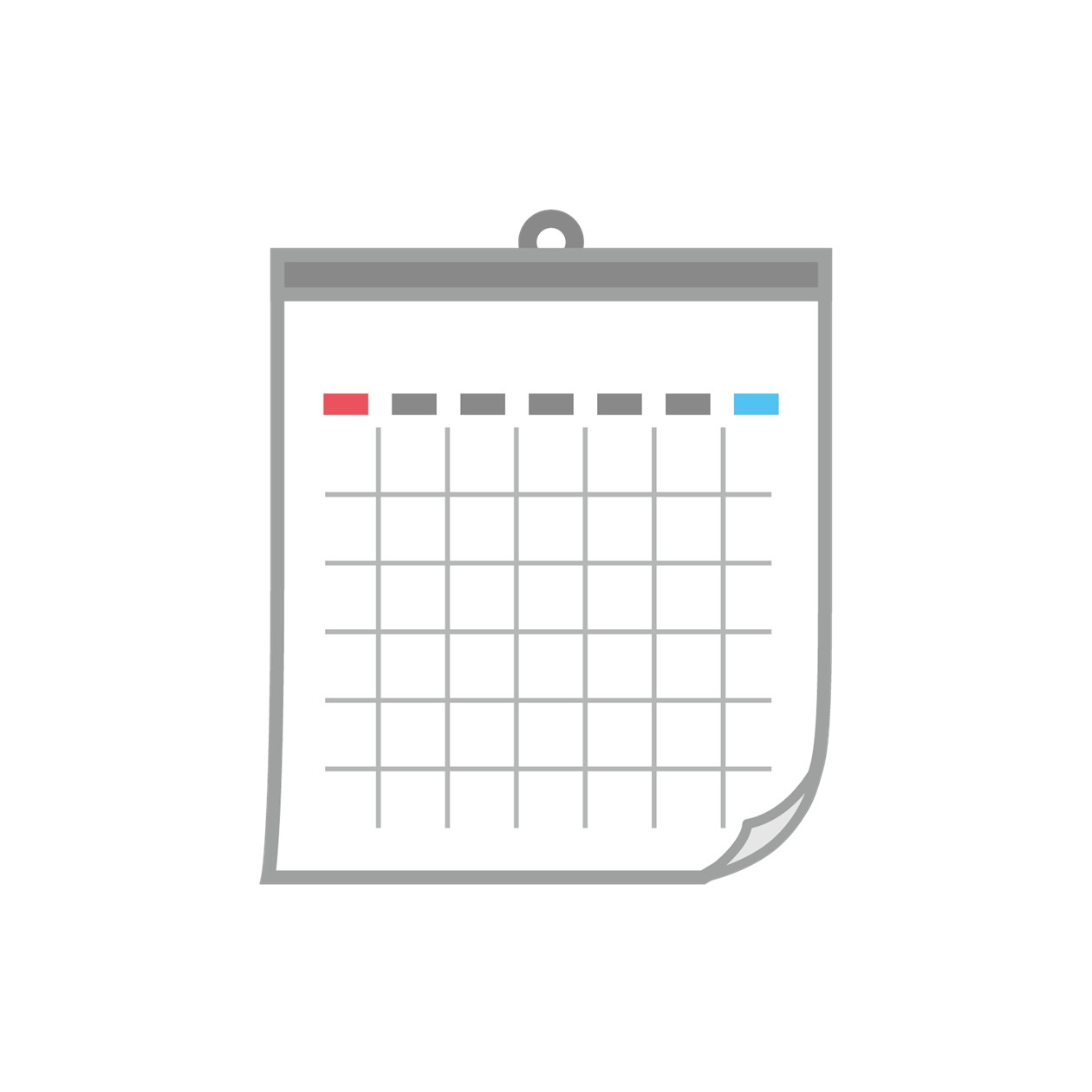
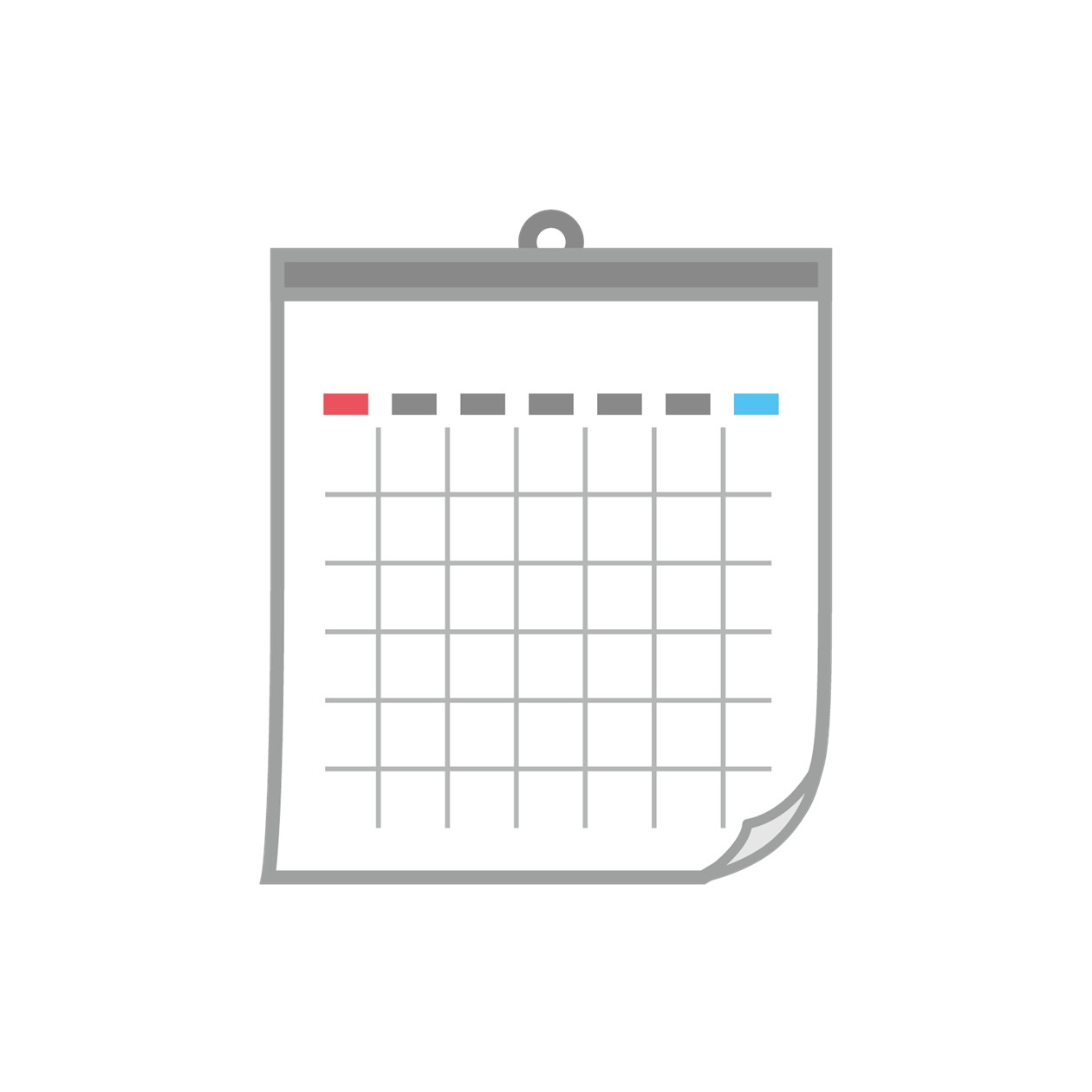
アルトコイン投資では、常に感情との戦いにさらされます。
この勝負に勝つための有効な方法が「売買ルールを事前に決めておく」ことです。
- 価格が$〇〇以下 or 以上になったら(あるいは指標が〇〇になったら)買う or 売る
- 〇〇月になったら買う or 売る
など、「どうなった時にどうするか」を自分なりにあらかじめ計画しておくことで、感情を切り離した投資ができます。
銘柄を知り、市場を知り、己を知れば、百戦危うからず
「アルトコイン投資は情報戦」だと考えています。
銘柄に対する理解、市場動向に対する理解、そして何よりも自分に対する理解を磨くことで、勝率を高め、負けた時の致命傷を避けられるはずです。
市場で長生きするためにも、情報の収集と取捨選択、自分との対話を心がけていきたいですね。